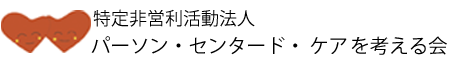抗精神病薬の弊害と特養でのケアを考える ~その2~
精神科の病院への入院については、ご家族としてはかなり否定的だったのですが、クリニックの医師から「しばらく経っても症状が変わらないということは、薬の影響というよりも認知症による症状であること、また、最近の病院の状況は思っているほど悪くないということ、一度入院したからといって一生過ごすわけではなく、改善したらまた戻ることができる」ということを説明され、病院をいくつか紹介していただいました。ご家族も納得され、入院加療の方向で調整が行われることになりました。しかしすぐに入院できるわけではなく、病院への事前の見学や面接をしたうえで、病院の空きがないと入院できないということで、しばらく特別養護老人ホームでの生活を継続することになりました。
職員が限界になっていたところでしたが、受診の翌日から入院に向けて動き出したところで、虚ろな表情から覚醒状態がよくなっていき、徐々にトイレの訴え以外の会話をしっかりとできるようになっていきました。抗精神病薬を中止してから、ちょうど2週間が経過したあとでした。
トイレ以外の会話も大幅に増え、特に食事についての話が多くなりました。それまでは、食事は飲み込みできず口からこぼれていましたが、しっかりと飲み込みできるようになり、「かりんとうが食べたい」「硬いものが食べたい」とはっきりとお話されるようになりました。ふと立ち上がり歩行されることはあるものの、それまではふらつき顕著にトイレへ向かおうとされるのみだったところが、足取りも良くなり、他の利用者様の居室へ入ろうとされたり、他の利用者様の食べ物を食べようとすることなど、トイレ以外への興味や移動も増えていきました。さらに食欲も出て、「お腹すいた」「甘いもの頂戴」等頻繁に話されるようになりました。それはそれで職員の対応も大変な部分もあるのですが、説明したりお話をお伺いしたりすれば、ご理解いただけるため、職員も誘導やお手伝いなどしやすくなっていきました。さらに徐々にトイレの訴えや不安が減っていき、夜間のトイレ回数も4~5回ほどで過ごせるようになっていきました。熟睡もされ、朝には「おはよう。よく眠れた」と言って起床されるようになっていきました。いつの間にか、職員から限界の様子はなくなっており、ある時「この状態なら病院へ入院しなくてもよいのでは」との話も出てきました。
入院にあたっての書類等も揃い、あとは具体的な入院日程を決める段階でご本人の様子が変わってきたため、再度今後の方針を施設内でも検討することとなりました。あれほど落ち着かずにいたご本人が、洗濯ものを積極的にたたんだり職員と談話するなどし、食事やおやつの時間を気にされるなど、時計を見ながら行動され、ようやくご本人らしい生活になってきていました。そのような中で入院することで、また環境が変わることや以前の情報から再度抗精神病薬が追加されたりすることになれば、またご本人の生活が変わってしまうのではないか、また落ち着かない生活に戻ってしまうのではないかという話になりました。ご家族にこのような状況になっていることをご説明し、もう一度入院について相談することとなりました。
結果、「できればこのままここで過ごさせてほしい」とのご家族のご意向があり、入院は一旦白紙に戻すことになりました。いろいろとご協力いただいた先生方にも説明をしたところ、特に問題になることはなく、引き続き施設で様子を見ることを了承いただきました。日が経つにつれご本人の様子はますます穏やかに、はっきりと会話も意思疎通もできるようになっていきました。職員の声掛けなどにもご理解をしっかりとされ、以前あった他の利用者様の居室へ入ろうとされたり、他の利用者様の食べ物を食べようとすることなどもなくなりました。自室にてご自身で乳液を塗るなど、お肌の手入れやおしゃれにも気を使われるようになりました。そして、リビングへ行き外の景色を見たりされ、「何もすることがないと眠くなるので、歩いてんだよ」などと表情豊かにお話されることも増えていきました。窓から外の景色を眺めることもあり、自宅近くの施設だったため、馴染みのある風景だとの話や、職員の名前も覚え、「この人におせんべいもらった」と笑顔でお話されたりもしていました。
先日、ご本人にこの施設に来た時のことを覚えていますか?と聞くと「覚えていない。何でここにいるのか分からない。でももう少し元気にならないと家に戻れないね。でも(ここでの生活も)楽しいよ」と話されていました。そして、他の利用者の方が食事でむせこんだりすると、背中をさすって気遣われるなど役割を持ち、自分の居場所としても認識されているようです。
薬の副作用が、この方らしい生活を送ることができなくなってしまったとことの大きな理由だったのだと思います。そのため、パーソン・センタードモデルの要素である「脳の障害」の医学的な部分はかなり重要なことだと思いますが、この方が今ここでこのように穏やかにその人らしい生活を送ることができるようになったのは、たとえ本人も覚えていなくても職員の関わりを実感しているからではないでしょうか。トイレ誘導に何十回と対応したり、安全のために見守り付き添いをしたり、その時々の状況に合わせて対応することが、この方にとっての心理的ニーズを満たしていたのではないかと考えます。また、実は意図してはいなかったのですが、パーソン・センタード・ケアの必須要素であるVIPSを実践していたのだと思います。I(個人の独自性を尊重したアプローチ)として、この方にとって意味のあることは何か分かろうと個別対応をしていたり、P(その人の視点に立つ)として、安全管理や環境設定などの配慮をしたり、S(相互に支えあう社会的環境)として、副作用でどうしようもない中でどうにか不安や苦痛に付き添ったことなど、それぞれ考慮したケアになっており、V(人々の価値を認める)の土壌があったから、組織として全職員がどうにか対応を継続してきたことに繋がっていたのではないかと思います。
入所当初のご本人の状況は、ご本人にもどうすることもできず、意識も朦朧としていたため、恐らくは状況の認識すらも困難だったと思います。薬の副作用で、座りたくても座れず、落ち着きたくてもじっとしていることもできず、立ち上がってもどうすることもできずに「トイレ」ということだけに意識が行ってしまうという状況は、ご本人にとって本当にとても辛く大変な体験だったと思います。もしあの状況で、何かケアのヒントを探そうとすぐに認知症ケアマッピングを行ったとしても、疾病としての診断や薬の見直しがなければ、そのようなご本人の体験を変えるような効果はほとんど得られなかったと思います。しかし、今行えばいろいろなケアのヒントが得られるのではないかと思います。認知症ケアマッピングは、パーソン・センタード・ケアを実践するためにとても素晴らしいツールだと思いますが、状況に合わせて使う必要があるのだとも実感しました。ただ、根底にはパーソン・センタード・ケアの視点をベースに持ったケアを行わなければ、この方が変わることはなかったのではないでしょうか。
(ある特養の相談員)